| 2004"9月25日 11歳「命」の詩
日増しに暖かく過ごし易い日が多くなってまいりました。皆様にはいかがお過ごしでしょうか?先日のお彼岸中、私は当家のお墓掃除をしようと墓地まで行きました。当家の墓地は10メートル程の短い坂道を登りきったところにあり、その途中にいくつかの檀家様のお墓があります。早速登って行くと既に何組かの方がお墓参りに来ておりました。私は小さいお子さんを一人連れたご夫婦に「こんにちは」と挨拶を致しました。当然のごとく返事があるだろうと次の言葉を用意しておりましたが何の返事もございません。確かに私も作務衣(僧侶の掃除服)にTシャツ、頭には白いタオルと和尚には見えにくく、お互い若い世代ですので面識も無かったでしょう。しかし、「面識がある、ない」、「お寺の人、そうでない人」に関わらず人に挨拶をされたら返すというのが当たり前ではないでしょうか?ましては子供さんがいる時には特に・・・
お釈迦さまのお教えに「和顔愛語」があります。常に穏やかな気持ち、笑顔で接することで人を幸せに出来る力があるという言葉です。私のような凡夫に出来ることは、まず第一に挨拶。きっとご家庭の中でも、「当たり前」が無いのだろうなと心配になってしまいました。
さて、今回は今年の朝日新聞に掲載された、ある少女の「命」の詩のお話です。(以下新聞参照)
舞台は長野県豊科町の県立こども病院。95年春、病棟の一角に小さな教室が出来た。小中学生10人ほどが、高さの違う机を丸く並べる「院内学級」だ。プリントを解いたり、習字をしたりして過ごす。先生の中の一人、山本厚男さんが、「感じたことを言葉に書くと元気がでる」と子供達に詩を勧めた。大きな紙に書き写し、廊下に張り出すと、みんな喜んだ。走りたい、退院したいという夢。家族への思い・・・。
その中に小学生の宮越由貴奈さんの詩もあった。由貴奈さんは小児がんの神経芽細胞腫を患い、抗がん剤治療や肝臓摘出手術などを繰り返していた。そんな状況の中、由貴奈さんもやはり詩に夢中になった。
「命」の詩は98年2月に生まれた。理科の授業で電池の実験をした。乾電池をつなぎ、電球がつくたびに「あ、ついた」と歓声をあげたという。この時の感動をもとに、命の大切さを問いかけた詩が生まれた。
その後、病状が悪化、98年6月、11歳で亡くなった。葬儀で参列者に詩のコピーが配られた。また、いじめの問題を抱える先生が朗読したり住職が法話で使ったりして口コミで広がっていった。その後、地元フリージャーナリストから角川出版の編集者の目にとまり、由貴奈さんら20人が書いた詩や絵を集めた詩集「電池が切れるまで」が出版された。
(以下に詩を原文のまま記す)
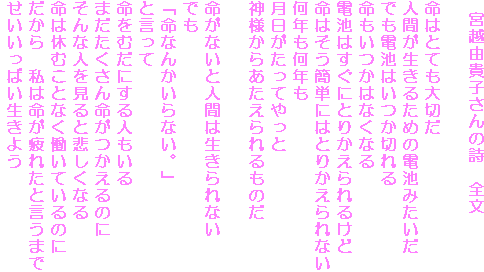 
写真・文 朝日新聞より
私達には、伝えられる口がある、言葉がある、沢山のものを見る目がある、匂いを楽しむ鼻がある、話を聞く耳がある、そして考えられる心がある・・・。どれ一つも私たちは無駄に使っていないだろうか?
今日から、今から、たった一言の挨拶「こんにちは」くらいは皆に言うべきであろう。
※この詩をモデルにしたドラマ「電池が切れるまで」はテレビドラマ(テレ朝)として放送されているそうです。
当山副住職合掌
|